モラハラ加害者のそばにいる人への被害は、単に「嫌な思いをさせられる」だけにとどまりません。
その被害は甚大で、たとえばモラハラをする上司がいる職場では部下に適応障害やうつ病患者が大量に発生したり、家庭内でもモラハラ夫を持つ妻がうつ病になったり、またその子どもは精神疾患を引き起こすとされています。
親が問題を抱えているケースではその子どもも高確率で精神疾患を発症することが知られており、モラハラ(自己愛性パーソナリティ障害)も例外ではありません。
父親が自己愛性パーソナリティ障害の場合、家庭総崩れの状態になる
父親が自己愛性パーソナリティ障害を抱えている家庭の場合、まずその影響が配偶者の妻に出ます。妻はモラハラ夫から受けた精神的負荷により、精神のバランスを崩し、さらにそれが子育てを通じて子どもへ影響を与えます。
子育て中の母親の精神状態がのちの子どもの人生に大きな影響を与えてしまうことは良く知られています。子どもはまず親との関係から人間関係の基礎とを学ぶようにできており、親との愛着の形が他の人間関係でも適用されるからです。
父親の問題は、母親に影響を与え、次に母親から子へと伝わっていきます。まるで水が高いところから低いところに落ちていくように、問題も上から下へと落ちていくのです。
こうして、家庭内のすべての人間に何らかの問題を抱える状態が出来上がってしまうのです。
自己愛性パーソナリティ障害を父親もしくは母親に持つ子どもの情緒面が不安定になる確率があまりにも高く、一般的な子どもに比べおよそ6倍とも言われています。
子どもはどんな子に育つ?
こうした環境で育てられた子どもはどんな風に育つのでしょうか?
上記の本では、パーソナリティ障害について詳しく分析されています。
この本の著者岡田尊司先生は、パーソナリティ障害を引き起こす根本的原因である愛着障害に関する本も多く執筆されていらっしゃいます。「なぜ夫はああなのだろう?」「なぜ職場の人はああなのだろう?」という疑問を本質的な問題に焦点を当てて解決してくれる本です。
愛着障害が元で、子どもが取る行動には「不安型」と「回避型」があり、回避型を取る子どもは将来自己愛性パーソナリティ障害になりやすいとのことです。
幼い頃に認められる回避型は…自己愛性パーソナリティや反社会性パーソナリティ、シゾイドパーソナリティに発展する方が典型的である。
この3つのパーソナリティには、大きな共通項がある。それは、共感性が乏しく、クールで、相手の気持ちや痛みに鈍感だということだ。
私は夫と接していると自分が物になったように感じることが多々ありました。その原因はこの本にも書いてあるように回避型の子どもはいずれ何らかのパーソナリティ障害を抱える可能性が高く、いずれもその性格は「相手の気持ちや痛みに鈍感」だからです。
そしてこれは、同じような環境で育てられた場合、将来自分の子どもがまたこのような性格になってしまうことも示唆しています。
離婚の影響だけでなく、結婚生活の影響も推して図るべき
このような状況になる前に、モラハラ加害者と離れたり距離を取ることを多くの専門書も推奨しています。
トラウマ研究の専門家ですら、自己愛性パーソナリティ障害の人の治療は困難を極めるとしています。専門家ですらそうなのですから、一般の人が相手を治そう、よくしようとしてもどれほど難しいことがよく分かるでしょう。そして多くの場合、問題のある配偶者にばかり目が行ってしまい、子どもへの影響に気づくことがありません。
家庭裁判所を通じて離婚の話し合いをするとき(調停、審判、裁判)、子どもがいる場合は離婚が子どもに与える影響のガイダンスを受けることができます。
離婚が子どもに与える影響については学ぶ機会がありますが、結婚生活で子どもにどんな影響があるのかについてまでは教えてもらえません。
離婚は子どもに影響を与えます。しかし、結婚生活においても深刻な影響を受けることがあることも事実です。
子どもが何らからの深刻な問題を抱えている場合、もしかしたらそれは離婚が原因ではなくて結婚生活の方に問題があった可能性もあります。特に幼少期の影響は大きく、多くのパーソナリティ障害を抱えている大人も、その原因の根本は幼少期にあることから、同じように子どもの幼少期に目を向けてみなければ解決しない問題であるかもしれないのです。
小さいうちは見えなかった問題が大人になってから顕在化することで、「今」の環境に何らかの問題があると誤認しやすく、またそのこと根本的な解決から遠ざかってしまいがちです。
苦しめている本当の原因がなんであるかを見極めるためには、当人の育ってきた環境を振り返ることも大事なのです。
自己愛性パーソナリティ障害については、こちらの記事に詳しくまとめています。↓
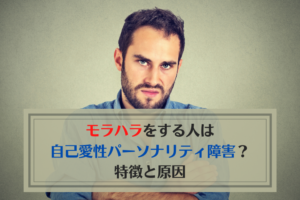
まとめ
子どもは親を選ぶことはできません。私は自分の子どもに対して、幸せな人生が送れることを強く願っています。
子どもの人生を幸せなものにするために、親が取らなければならない行動はとてもシンプルです。
それは子どもを愛し、尊重すること。そのたった2つのことで、子どもの人生は大きく決まります。
モラハラ加害者がいかに多くの被害を生むのか、そしてその悲劇の連鎖がいかに引き継がれやすいものなのか。
モラハラを治したいと思っている人も、モラハラやDVや虐待の被害に遭っている(もしくはあっていた)人も一度岡田先生の本を読んでみることをオススメします。




コメント