モラハラ加害者と生活を続けていると、精神的に相手から支配を受けるようになり、「夫がいつも正しくて、妻がいつも間違っている」構図が出来上がります。
自分が決めたことがいつも否定されることで、次第に自分のことでも自分で決めることが悪いことであるように思い込んでいきます。
そして、モラハラ加害者に従うようになってしまうのです。
その時の私は、夫の機嫌で私の人生のすべてが決まるような気になったり、私が働いたり、どこに出かけるのかもすべて夫が決めるものだと思ってしまっていました。
夫からの精神的支配は、自分と夫の境界線が分からなくなることにより引き起こされていました。
他人との境界線を引くことがなぜ大事なのか、そして他人との境界線をうまく保つためには何をすればいいのかをまとめました。
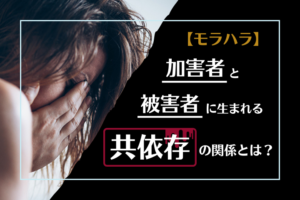
私の体験談
具体的な私の思い込みには次のようなものがありました。
たとえば、
- 夫が近所の人に怒鳴りつけたりしたことの責任は私にあり、謝罪などはすべて私がしなくてはいけないと思っていた
- 自分の外見や行動について、夫や義両親から「こうしなくてはいけない」と強制され、それを忠実に守らなくてはならないと思っていた
- 夫から、「母親はこうあるべき」「仕事はやめるべき」と価値観を押し付けられ、自分が何を大事にしたいかが分からなくなっていた
とにもかくにも、私は自分のことを意思決定する権利がないと思っていました。
「私と夫は別の人間であり、別の価値観を持ってい別の行動を行うものである」ということがモラハラ行為を受け続けることによって次第に分からなくなっていました。
一番の原因は夫からの支配によって、私は夫の言うとおりに動かなければならず、夫と私は同一的な存在だと思い込んでいたことによるものです。
このように他人との境界線が分からなくなると、人に支配されやすく人の気分に左右されたり、人の機嫌を取らなくてはならないような気がしてしまいます。
自分の意思を侵略されないために、他人と適度な距離を取り、「人は人、自分は自分」の境界線をハッキリさせることが必要です。
他人との境界線をハッキリさせるためには?
①行動の責任を明確にする
その行動を取った時の責任が誰にあるのかを考えましょう。
例えば、自分が責任を取らなくてはならないことは、自分に決定権があるハズです。自分が責任を取らないといけないのに、決定権だけ他人にあるのはアンバランスですよね。夫が干渉してきたとしても、相手が責任を取ってくれないことに対して決定権を委ねてはいけません。
自分がどこまでの責任を負うのかをもとに、自分の行動をどうしたらいいのかを考えましょう。
逆に、夫が取った行動の責任は夫自身にあります。家族ですが、もう立派な大人ですから自分で責任を取れないようなことは本来はすべきではありません。
このことから、モラハラ加害者の常套句である「お前のせいで俺は怒鳴っているんだ!」という行動の責任を人のせいにするセリフが、いかにおかしいかに気づくことができるでしょう。
②彼らから貼られるレッテルを信じない
モラハラ加害者はターゲットを勝手に「○○な人」だと定義します。レッテルを貼ることではターゲットを扱いやすい人にするためです。
レッテルは人を言語化します。言語は思考に影響が及びます。
つまりマイナスなレッテルを貼られた人は、そのマイナスな言葉によってマイナス思考に囚われます。
彼らの失礼なレッテルを信じないこと、彼らからの評価に執着しないことが境界を保つために必要です。
子どもができると、夫から「子育ては母親がやるものだ」「母親は働いていはいけない、今すぐ仕事を辞めろ」と言われました。
この時はすでに夫のモラハラは加速しており、夫の価値観がすべて正しく、私が何か意見をしようものなら「母親失格だ」とレッテルを貼って自分の意見を通していました。もちろん世間では、子どもを預けながら働いている人も多くいますし、そのことで母親失格と決めつけることはできません。しかし、その時の私は、自分が働く=子どもより仕事を優先しているダメな母親=母親失格のような気がして、仕事を辞めてしまったのです。
「母親失格」にならないように自分で境界線を移動してしまったのです。
③自分の価値観を振り返る
相手に境界線を侵食されると、相手の価値観を自分の価値観と同じだと思い込むようになります。モラハラ加害者の言うことが正しく、自分は正しくないと思っていませんか?
自分の価値観が分からなくなってしまったときは、相手が境界線を踏み越えてきている証です。
自分が何が好きで何が嫌いなのかをよく思い出してみてください。
そうすることで境界線のスタートがどこにあったのか思い出せるはずです。
④「できること」と「できないこと」を明確にする
たとえば、夫婦二人暮らしだったのが子どもが生まれ三人暮らしになると子育てに時間を割かれるため夫婦二人暮らしの時とは時間の使い方が大きく変わります。今までできていたことができなくなることもあります。
1日の時間は24時間と変わらない中で、子育てのタスクが増えたのにもかかわらず、今までと同じように家庭のことをやることは物理的に不可能です。
無理なことをすることは「努力」ではありません。努力というのは自分の力を尽くすことです。
自分には何ができて、何ができないかを明確にしましょう。
自分のできる範囲外れることは相手から強要されることではありません。
私が夫からよく言われてた言葉に「努力が足りない」というものがありました。
私が「朝は授乳などで時間が取られるから、以前と同じ朝食を用意できない。一品減らしてほしい。」とお願いしたときは、夫は「お前の努力が足りないからできないのだ。もっと努力しろ。」と言っていましたし、
夫が職場での人間関係がうまくいっていないことについても「お前の内助の功が足りないからだ。だから俺が職場でミスをしてしまうんだ。」とも言っていました。
私が努力したところで、物理的な時間の足りなさや(睡眠時間を削ればできますが根本的な解決ではありません)、夫の職場での人間関係をどうこうすることはできません。
それは私ができないことだからです。
努力とは、「睡眠時間を減らして朝食を作る時間を増やす」ことでも、「夫のご機嫌を取るためにサンドバッグになる」ことでもありません。
- 他の人がやるべきことをやらないこと
- 責任の所在をハッキリさせ相手の責任と自分の責任を分けること
- 他人の問題を自分の問題にしないこと
- 彼らの言葉に囚われないこと
対処法は?
自分で境界を引くことと、相手が境界線を越えてくるのを阻止することが必要
そして、モラハラ加害者はズカズカと境界線を乗り越えてきます。それを阻止して、乗り越えさせないことも必要です。
具体的には、自分が「いやだ」と思ったらそれをその場で表現することです。相手から良い反応をもらいたいからといって自分の感情を押し殺したり、自分に無理をさせてはいけません。
大切なのは、相手に合わせて自ら境界線の位置を下げたりしないことです。
自分で自分の境界線を守りましょう。
相手がモラハラ加害者である場合は、彼らは何度も境界線を越えようとトライを繰り返します。彼らと過ごすということは、境界線をキープする戦いが繰り返されるということです。
ゴール(最終的に境界がどうなったのか)は徐々にずらされていくためにずらされたことに気づかないことがあるので、自分の最初の立ち位置とゴールを常に把握してください。
境界を相手に知らせないことも有効
意見が対立したときに、「ここまでなら譲っていい」という情報を相手に伝えないことも有効だと言われています。
まず相手が何を望んでいるかを聞いて、それについて「イエス」か「ノー」かを答え、自分の境界を相手に知られないようにしてください。
最終的には距離を取る
あらゆる虐待や加害がある関係において健全な境界は存在しません。 虐待者や加害者は、ターゲットの全てに対して口を出す権利を持っていると考えています。
一緒にいると境界を保つことができない相手もいます。そういう人からは離れるしか解決方法はありません。
 葛藤ナマモノ
葛藤ナマモノ私の場合離婚して今は境界線も正常になりました。だからといって「いま会えば平気」とは思いません。 境界線は鉄壁の守りではなく揺らぐもので、だからこそモラハラ加害者のように境界線を攻撃してくる人と一緒に居たくないと思えるようになりました。
まとめ
窓があれば、外に飛んでいるスズメバチに怯えなくてすみます。
しかし、自ら窓を取り外して境界線を無くしてしまえば、いつ家の中に入ってくるかわからないスズメバチに怯えなくてはならなくなります。
他人との境界はまさにこの窓そのものです。
自らの境界線を他の人に越えさせないことは、自分を守るためだけではありません。
相手が境界を踏み越えてきそうなときにハッキリと「NO」と伝えたときに、その人が「良い人」であれば、二度と同じ境界を越えてくることはありません。つまり、あなたにとって「付き合うべき人」かそうでない人かが見えてくる指標ともなりえるのです。
人に「NO」を突き付けるのは、自分自身も嫌な思いをしなくてはなりません。ですが、勇気を出して「NO」を言ったときに相手が「信頼」できる人物かが分かり、また相手との信頼関係を築く礎となるのです。
「NO」と言ってもズカズカと踏み込んでくる人には当たり障りのない人間づきあいにとどめておきましょう。
そしてあなた自身も他人の境界線を踏み越えることのないようにすることが大切です。
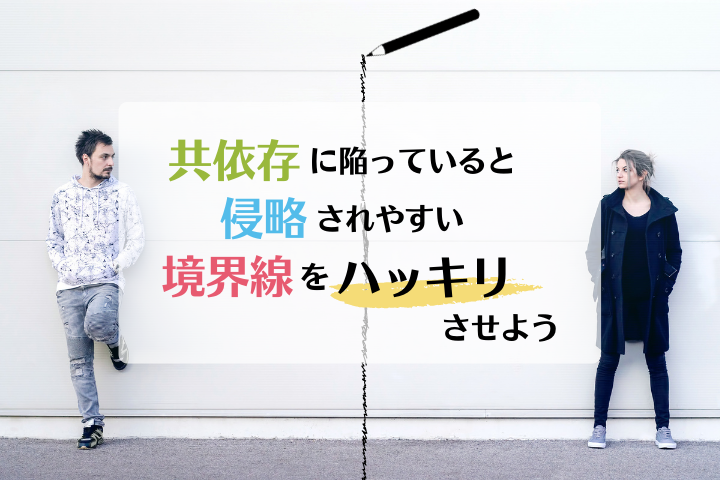
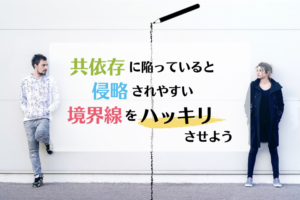
コメント