子どもの目の前で夫婦喧嘩をやっていませんか?子どもにとって「目のまえで両親の争う姿」を見せられることは百害あって一利なし!全くいい影響を及ぼさないどころか、修復できない脳への影響を与えるということが分かってきています。
でも、暴力もないし、ただの言葉の言い合いなんだけれど…。
と思っている方がいらっしゃれば、ぜひお伝えしたい耐衝撃の事実があります。
それは、「精神的な暴力や暴言(モラハラ)の方が子どもの脳に深刻な悪影響を与えるということ」です。
ただの言い争いだからと思っている場合は、その認識を改めたほうがいいでしょう。言い争いが招くのは、「暴力を見せられるよりももっとひどい悪影響」を子どもの脳に残すということです。
お子さんがいる家庭でモラハラ被害に遭っている方にはぜひ知ってもらいたい情報です。モラハラ被害がもたらすのは精神的な被害だけにとどまりません。のちの人生にも大きく影響を与える「脳のダメージ」についても知り、考えなくてはいけません。
子どもの目の前で暴力・暴言・モラハラを見せると何が良くないの?
子どもの目の前で夫婦喧嘩(暴言・暴力・モラハラ)をするとどんなことが良くないのでしょうか?
どんな家庭でも起こりうる夫婦喧嘩ですが、その内容や頻度によっては子どもに重大な悪影響を与える恐れがあります。
子どもが直接の暴力や暴言の被害者でなくても、それを見せられている子どもには心や脳にダメージを与えることが分かってきました。
身体的暴力を見せられるより暴言や怒鳴り声を聞かされる方が子どもの脳は委縮する
暴力を見たことがある子どもは経験のない子どもに比べて脳が「3.2%」も委縮していた(萎縮率)そうです。
一方で、両親の言葉の暴力をみてきた子どもは経験のない子どもに比べてなんと「19.8%」も委縮していたことがわかりました。
つまり、言葉の暴力の方が子どもの脳へより深刻なダメージを与えていることが分かります。
参考:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscap/57/5/57_719/_pdf/-char/ja
脳の萎縮が見られた子どもは「日常的」に暴言を耳にしていた
どのくらいの暴言によって脳が委縮するのかを調べたテストでは、その内容と頻度によって点数が付けられ、合計した点数で「どれくらい暴言にさらされているのか」を数値化しました。
そのテストは以下の通りです。
一方の親がもう一方の親に対して、
- 叱りましたか?
- 大声を上げましたか?
- 罵りましたか?
- 行ったことを責めましたか?
- 辱めましたか?
- 危害を加えると脅かしましたか?
- 気分を悪くするような悪口を言いましたか?
- ばかで、行動が幼稚だと言いましたか?
- 行わなかった行為について責めましたか?
- 人前でバカにしたり、恥をかかせましたか?
- 批判しましたか?
- 明らかな理由なしにヒステリックに怒鳴りつけましたか?
- 無能で価値のない人間だと言いましたか?
- 無能で価値のない人間だと感じさせるようなことを言いましたか?
- 声を荒げましたか?
これらの項目について、それぞれ
- 毎日あった:7点
- 週に2~3回:6点
- 毎週:5点
- 毎月:4点
として集計していきます。あったかなかったかだけではなく、その頻度も重要なパラメータです。
しかし、点数を見ても分かるように「毎日」と「毎月」では目にする機会は約10分の1~約30分の1ほどにはなりますが、点数としてはそれほど大きな差がないことに注意しなくてはいけません。夫婦喧嘩の頻度がたとえ月に1回程度であったとしても、子どもへの影響を考えなくてはいけないということです。
このテストでは、子どもが小さくテストに答えられないうちからでも親本人がテストを行うことで、子どもへの悪影響がどのくらいになるのかを把握することができるというメリットがあります。
さて、結果は…
合計が40点以上であれば、脳の萎縮が見られたそうです。
全部で15項目あるため、すべてにおいて月に1回程度当てはまる場合は、それだけで60点になります。頻度も重要ですが、網羅性が高い場合も同様に悪影響が強いことが伺えます。
また、DVやモラハラには周期があり、『1.緊張状態が蓄積していく時期』⇒『2.怒りが爆発する時期』⇒『3.やさしくなる開放期(ハネムーン期)』を繰り返すと言われています。
つまり時期によって加害行為の頻度や内容が大幅に変わることになり、ある時には点数が低くてもまた別のある時には高くなることもあります。
時期によって点数が変わることをあらかじめ考慮しなくてはならず、たとえ今の点数が低かったとしても過去に点数の高い時期があるのであれば注意をしなくてはいけません。
◆関連記事◆
脳の「扁桃体」「海馬」に異常が現れる
高い頻度で暴言を目の当たりにすると、脳が委縮するということがわかりました。
この時、脳の中では何が起こっているのでしょうか?
日常的に暴言にさらされている子どもは、脳の扁桃体や海馬に異常をきたしてしまうと考えられます。ストレスを感じた際に出るコルチゾールと言うホルモンが、脳を攻撃するためです。
扁桃体…恐怖、不安、悲しみ、喜びと言った感情やそのコントロール。
海馬…短期記憶を司る。恐怖、攻撃、性行動、快楽などにも関与。
恐怖にさらされているために、常に扁桃体と海馬に刺激が行き、扁桃体は刺激を受けて大きくなります。海馬はストレスホルモンによって攻撃を受け、小さくなります。また、記憶を司る部分でもあるので記憶力が低下します。
扁桃体は大きくなった結果、刺激に対して過敏に反応を返すようになり、少しのことでも強い恐怖や不安を感じたり、怒りやすい性格になります。
その結果、「恐怖や怒りを感じやすい」「感情のコントロールができにくい」「なにかにつけてキレやすい」「学習意欲の低下」「記憶力の低下」が見られるようになってしまうのです。
脳にダメージを負った子どもが成長して大人になると、キレやすいためにささいなことで「暴言」「大声を出す」ようになります。家庭をもつと同じように夫婦喧嘩が頻繁に起こり、今度はその子供が脳のダメージにさらされます。こうして、次の世代にも「キレやすさ」が連鎖していくと考えられます。
暴言・モラハラのトラウマは癒すのが難しい
暴言やモラハラのトラウマほど癒すことが難しい、と臨床現場にいる方は感じているそうです。
両親の激しいケンカを目の当たりにしてきた子どもたちには、同じような暴言を吐いたり、感情がコントロールできない子が多いといわれています。そして、たとえ環境が変わったとしても攻撃的な態度はすぐに変わることはないようです。
こういった子どもたちと接している精神科医の方は、暴言のダメージの大きさや、暴言によるトラウマの取り除きにくさを実感すると言います。
子どもの不登校は離婚が原因?それともそれまでの家庭生活が原因?
離婚家庭の子どもは、「不登校」「適応障害」「うつ」といった二次的な弊害が見られることが多々あります。しかし、これがそもそも「離婚」が原因なのか、それまでの家庭生活での慢性的なストレスが原因なのか、判別が難しいとも言えます。
周囲は、「離婚」が子どもから健康を奪ったと考えがちですが、離婚以前の家庭生活の方が問題であり、長年の悪影響が今になって現れたということもあります。
ストレスによる症状と言うのは「リアルタイムで出ない」ことから、ストレスがなくなってしばらくしてから症状に悩まされることがあるからです。
すると、その直前のできごとが「原因」であると誤解されやすく、本当の「原因」が別のところにあったとしても気づかずに見過ごされてしまうのです。
子どもの脳を傷つけないためには、モラハラを見せない
「子ども自身が被害に遭っていないから」
「暴力がないから」
と言った理由で「大丈夫」だと思い込むことがいかに間違っていることか分かるかと思います。
たとえ、子ども自身が被害に遭っていなかったとしても、暴言だけであったとしても(むしろ暴言の方こそ)子どもへの重大な悪影響を与えてしまいます。
そして、何の原因も責任もない子どもが、暴言や暴力の割を食わなくてはいけなくなってしまうのです。
「夫婦喧嘩は犬も喰わない」といいますが、残念ながら子どもは喰ってしまいます。そして、一度ダメージを負った脳は回復が難しく、大人になってからも悪影響に悩まされることもあります。
脳の後遺症は、本人の責任ではありません。しかし、世の中から見れば「キレやすく付き合いづらい人」と言うレッテルを貼られ、人間関係がうまくいかなくなることもあります。
親は、夫婦喧嘩が子どもへどんなリスクがあるのかをしっかりと把握し、子どもの目の前で夫婦喧嘩をしないように心がけなければいけません。
しかし、パートナーがそうは思ってはいなかったり、あえて子どもを巻き込んで夫婦喧嘩をする場合には、別の手を打たなくてはいけないと考えます。
◆関連記事◆
その他の虐待や夫婦間の暴力による子どもの脳への影響の研究(https://www.researchgate.net/publication/308303380_The_effects_of_childhood_maltreatment_on_brain_structure_function_and_connectivity)
もし、子どもへの影響が出たとしたら?自分の生きづらさを解消したいときは?
暴言によるトラウマは取り除くことが難しく、脳のダメージも回復しづらいということが知られています。しかし、決して治らないということはなく、大人になってからも脳のダメージが回復できたという研究もあるそうです。
生きづらさの原因は、本人のせいではありません。
しかし、他人のせいにして「生きづらさ」から逃げようとしても、さらに苦しみが続いていくだけです。
「生きづらさ」の原因が、幼いころの家庭環境やトラウマ体験であると気づいたのであれば、自分で生きづらさを解消するための行動を起こさなくてはいけません。
認知行動療法を学び、自分の固定された考え方を変えてみたり、マインドフルネスを学ぶことも効果があるようです。
また、自己心理学によってトラウマの原因を把握したり、自分に欠けているものを知ることにも意味があります。
親は、子どもに共感し、子どもを認めていくことで脳が回復していくようです。子どもがやっていることを肯定的にとらえ、言葉にしてかけてあげてください。
大切なのは、もう取り戻せないとあきらめることではなく、未来を変えるために行動をし、自分を良くしていくことです。
◆関連記事◆
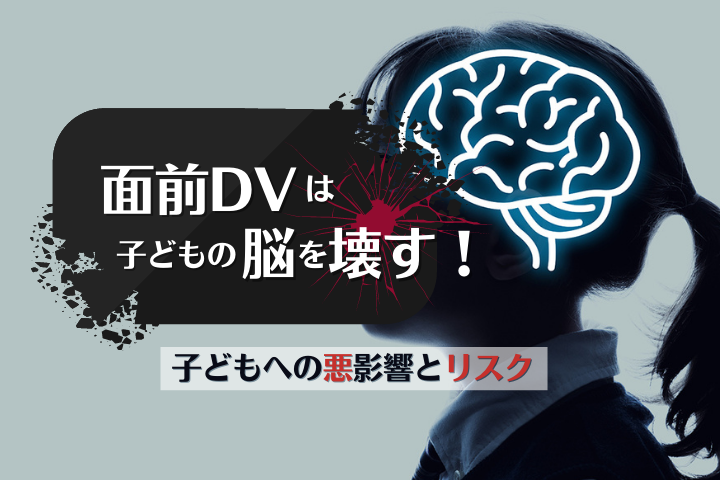
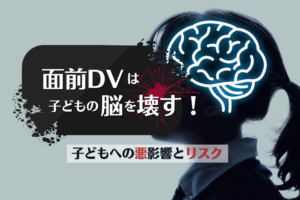
コメント